高血圧症

高血圧症は、自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行することがあります。放置すると動脈硬化や心疾患、脳卒中などの重大な病気のリスクが高まります。食生活の乱れやストレス、肥満が原因となることが多く、生活習慣を見直すことが重要です。
しかし、生活習慣の改善だけではコントロールが難しい場合もあり、その場合は薬物治療を併用することが必要です。
当院では、高血圧症の治療に積極的に取り組み、患者さまに合った治療方法を提案します。
高血圧症が引きおこす疾患
-
網膜症・眼底出血
眼の細い血管がもろくなると、破れて出血し、眼底出血を引き起こすことがあります。糖尿病や高血圧症などが原因となることが多く、初期には自覚症状がない場合もありますが、進行すると視界がかすむ、黒い影が見えるなどの症状が現れることがあります。
さらに悪化すると、視力の低下につながる可能性があります。 -
腎不全
腎臓は細かな血管が集まった臓器であり、高血圧症の影響を受けやすく、動脈硬化が進行すると腎機能が低下し、腎不全に至ることがあります。自覚症状はほとんどありませんが、進行すると尿の異常やむくみ、倦怠感などが現れることがあります。
さらに悪化すると、腎機能の回復が難しくなり、最終的には透析療法を続ける必要が生じることがあります。 -
脳梗塞・脳出血
動脈硬化が進行すると、血管が狭くなったり詰まったりして血流が悪化し、脳の血管に障害が生じることがあります。
その結果、脳梗塞や脳出血などの重篤な疾患を引き起こし、手足の麻痺や言語障害、意識障害が現れることがあります。
発症後は後遺症が残ることも多く、重症化すると生命の危機に直結する可能性もあるため、早期の予防と管理が重要です。 -
心臓病
冠動脈と呼ばれる心臓に栄養を供給する血管が動脈硬化を起こすことで、血管が狭くなる狭心症や血管が詰まる心筋梗塞などの疾患を引き起こすことがあります。
さらに、長期間の高血圧症は心臓に負担をかけ、心筋肥大を招き、進行すると心不全のリスクが高まります。 -
大動脈瘤・大動脈解離
高血圧症の影響で、大動脈がこぶ状に膨らみ、もろくなることで大動脈瘤が生じることがあります。
また、血管壁が裂ける大動脈解離を引き起こすこともあり、いずれも進行すると重篤な状態につながる可能性があります。
大動脈は全身に血液を送る重要な血管であり、破裂すると命に関わる危険な状況となるため、早期の発見と対応が重要です。
高血圧症の主な原因
- 過剰な塩分摂取
- ストレス
- 肥満
- 自律神経の乱れ
- 過剰飲酒
- 運動不足
- 喫煙
- 原発性アルドステロン症
- 腎動脈狭窄
- 褐色細胞腫
- 睡眠時無呼吸症候群
- 甲状腺機能亢進症
高血圧症の治療方法
食事療法

高血圧症の食事療法では、塩分を1日6g未満に抑え、野菜や果物、全粒穀物、魚などの摂取を心がけることが重要です。赤身肉や加工肉を控え、飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を摂取することが大切です。適正体重を維持し、アルコールやカフェインの摂取を控えましょう。
規則正しい食生活を意識し、DASH食を取り入れるとともに、医師や栄養士と相談しながら実践することがすすめられます。
運動療法

高血圧症の運動療法では、有酸素運動を習慣的に行い、週に数回、30分以上の運動が推奨されます。中等度の強度で血管機能が改善され、降圧効果が期待できます。膝や腰に負担の少ない運動を選び、筋力トレーニングも有効です。
運動前に医師のアドバイスを受け、異常を感じた場合は中止し、相談してください。
無理なく継続することで、血圧管理や心血管疾患のリスク低減が期待できます。
薬物療法
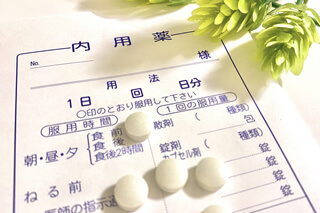
高血圧症の薬物療法では、ACE阻害薬・ARB・カルシウム拮抗薬・利尿薬、β遮断薬などが使用され、血管を広げたり、心拍数を減らしたりします。患者さまの状態に応じた薬が選ばれ、生活習慣の改善と併用することで効果が高まります。継続的な服用と定期的な血圧測定が重要で、医師の指示に従うことが求められます。
薬物療法は長期的な血圧管理に役立ち、合併症の予防に効果的です。
